先日、インダス文明とメソポタミア文明の社会構造の違いを取り上げた番組を観た。
インダス文明には王の存在も、宗教や武器の痕跡もなく、宗教や武力によって統治された国家の形を持たずに繁栄していたという。歴史の授業で学んだ「文明=支配と権力の象徴」というイメージとは大きく異なり、とても興味深かった。
歴史の見方は、時代とともに変わっていく。
たとえば、日本史でも鎌倉幕府の成立年が「1192年」から「1185年」に改められたり、江戸時代の「士農工商」という身分制度が実際には存在しなかったとされるなど、常識が塗り替えられてきた。一度「正しい」と教わった歴史が覆ると、戸惑いと同時に、過去への理解が少し自由になるような気がする。
その背景には、新しい史料の発見や研究技術の進歩もあるが、それだけではない。
調査する人の時代や関心が変わることで、同じ出来事を別の角度から見つめ直すことができるのだ。「事実」は一つでも、「解釈」は無数にある。そこに歴史の面白さと、人間の限りない想像力を感じる。
歴史だけではない。
私たちが日々見ている世界も、立場や経験によってまったく違って見える。「こうに違いない」と決めつけず、いくつもの見方を持つこと――それが、変化の多い時代を柔軟に生きるための知恵なのかもしれない。
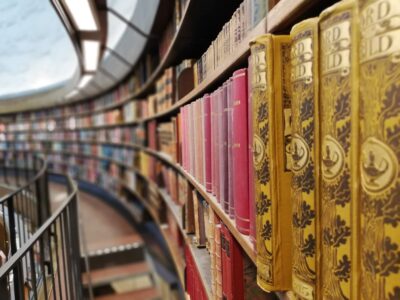
経営企画部 府中

